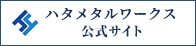アルミニウムは磁石につかない?その理由と意外な活用法
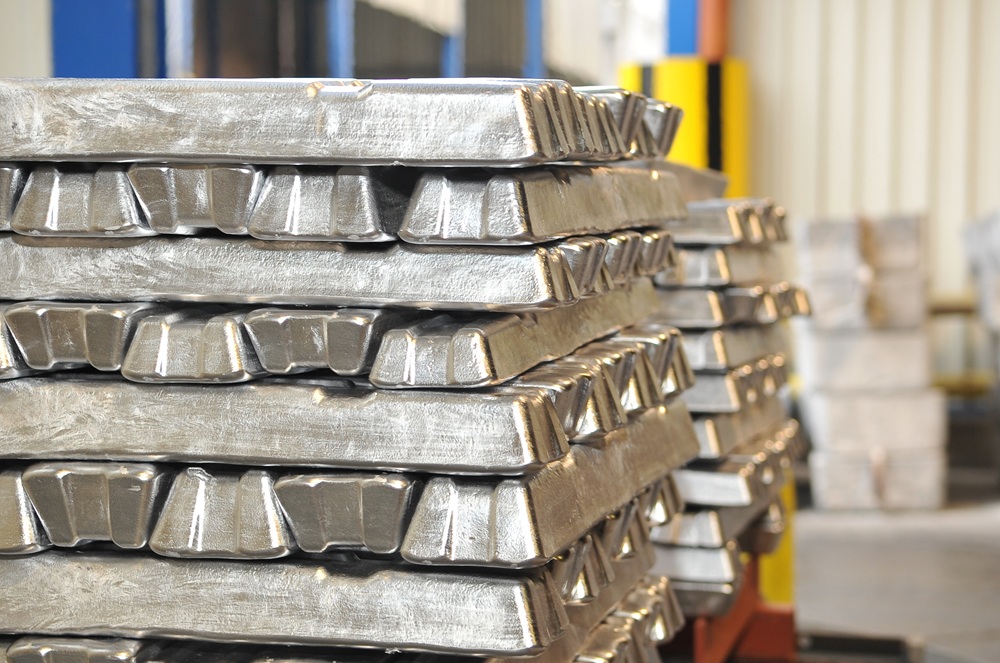
アルミホイルや飲料の缶、スプレー容器など私たちの身近には「アルミニウム」を原料とした製品であふれています。アルミニウムも鉄と同様金属に分類されますが、磁石にはくっつきません。同じ金属なのにこれはなぜなのでしょうか?この謎について解説します。
磁性とは
磁性の基本原理
磁性とは、ある物質が磁石に引き寄せられる力のことです。アルミニウムは非磁性の金属なので、磁石に引き寄せらせません。
少し専門的な話になりますが、磁性は原子構造に関係します。磁性は、原子核の中で最も外側の軌道を回る電子の性質に起因するものです。電子の回転は円状の電流と同じと考えられるので、その周辺には棒磁石と同じ形の磁場ができ、これを「原子の磁気モーメント」といいます。
ほとんどの原子は単体で磁気モーメントを持ちます。しかし原子単体だと不安定なため、分子や結晶になったり、結合して金属に変化したりするのです。その際アルミニウムをはじめとした多くの物質では、外側の電子同士が同じ軌道を逆に回る組み合わせとなり、磁気モーメントが失われてしまいます。
一方、鉄やニッケルなどの原子は、最も外側からひとつ内側に特殊な軌道があります。この軌道を回る電子が、化合物や結晶の中で一定の方向に回るため、磁気モーメントが失われることはありません。磁気モーメントを持つ鉄などの物質は、小さな棒磁石と考えられるので磁石にくっつくということになります。
アルミニウムは常磁性
磁性は物質ごとに強さや性質が異なるものの、大まかに強磁性・常磁性・反磁性の3つに分けられます。簡単にいうと、磁石にくっつくのが強磁性、磁石にほとんどくっつかないのが常磁性、磁石から離れるのが反磁性です。
アルミニウムは常磁性に分類されます。磁界の中に置かれると、外部磁界と同じ方向に弱く磁化されます。しかし、この磁化力は非常に弱いので、磁石にはくっつきません。また外部磁界を遠ざけるとアルミニウムの磁化もなくなります。常磁性はもっとも一般的な磁性で、アルミニウムのほかチタン・酸素・ナトリウムなどたくさんの物質が含まれます。
ちなみに強磁性に分類される鉄は、磁界中に置かれると磁界と同じ方向に強く磁化され、外部磁界を遠ざけた後も磁性は保たれます。常温で強磁性を示す金属は、鉄のほかにコバルト、ニッケル、ガドリニウムの4種類しかないのでとても珍しいケースだといえるでしょう。
磁性金属と非磁性金属の一覧
一般的な金属の磁性を分類すると以下のようになります。
- 強磁性金属:鉄、ニッケル、コバルト、ガドリニウム
- 常磁性金属:アルミニウム、チタン、マグネシウム、白金、パラジウム
- 反磁性金属:銅、銀、金、鉛、水銀
これらの分類を知ることで、用途に応じた適切な金属選択が可能になります。
アルミニウムの特性と活用法
アルミニウムという金属の特徴は、軽量・優れた熱伝導性と電気伝導性・耐腐食性が高い・強度に優れている・磁場の影響を受けないことが挙げられます。
鉄や鋼と比較すると非常に軽いので、構造材料として使われています。また熱伝導性と電気伝導性が優れていることから、電子機器や電気配線にもよく使われる素材です。
アルミニウムは酸化皮膜(金属表面にできる微細なサビ)を自然に形成します。酸化皮膜は耐腐食性を高めるため、外部環境にさらされる場所でも長期間使用することが可能となります。
加えて、アルミニウムは非常に加工しやすいのも特徴です。薄い板状、細いワイヤーなど様々な形状に加工できるので、建築材料・包装材・航空機や自動車の部品など広く利用されています。
そして磁場の影響を受けないので、電子機器や航空機の部品としても最適な素材なのです。
非磁性を活かした具体的用途
アルミニウムの非磁性という特性は、様々な分野で重要な役割を果たしています。
- 医療分野でのMRI室内装備
MRIは強力な磁場を使用するため、室内の什器や機器にはアルミニウムなどの非磁性金属が使用されます。これにより画像の乱れを防ぎ、患者の安全も確保できます。
- 磁気カードリーダーの筐体と部品
クレジットカードや交通系ICカードなどの読み取り機器では、外部磁場による干渉を避けるためアルミニウム製の筐体が利用されています。
- 精密電子機器の電磁シールド
アルミニウムは電磁波を遮断する性質があるため、パソコンや通信機器の内部シールドとして使用され、電磁干渉から回路を保護します。
- IC設計と半導体製造
半導体製造プロセスでは、磁場の影響を受けにくいアルミニウム配線が使われ、安定した電子回路を実現しています。
このように、アルミニウムの非磁性という特性は現代のハイテク機器や精密機械において欠かせない要素となっています。
よくある質問 (FAQ)
Q: アルミホイルは本当に磁石につかないのですか?
A: はい、一般的な磁石ではアルミホイルはくっつきません。アルミニウムは常磁性体であり、通常の磁石で使われる磁場の強さでは引き付ける力が非常に弱いためです。ただし、非常に強力な電磁石や特殊な条件下では微弱な反応を示すことがあります。
Q: アルミとステンレスの磁性の違いは何ですか?
A: アルミニウムは常に非磁性ですが、ステンレスは種類によって磁性が異なります。オーステナイト系ステンレス(SUS304など)は非磁性ですが、フェライト系ステンレス(SUS430など)は磁石にくっつきます。これは含まれる鉄やニッケルの量と結晶構造の違いによるものです。
Q: 非磁性金属でも電流を流すと磁性を帯びるのはなぜですか?
A: 電流が流れると周囲に磁場が発生します(電磁誘導)。アルミニウムなどの非磁性金属でも、電流を流すと一時的に磁場を生じますが、電流が止まれば磁性も消失します。この原理はモーターやスピーカーなど様々な電気機器に応用されています。
Q: アルミニウムで作られた物体に強力な磁石を近づけると動くことがありますが、これはなぜですか?
A: これは「渦電流」と呼ばれる現象によるものです。強力な磁石をアルミニウムに近づけたり動かしたりすると、アルミニウム内部に電流(渦電流)が発生します。この渦電流が磁場を作り出し、元の磁石との間に反発力や吸引力を生じさせるのです。この原理はアルミニウム製ブレーキや金属探知機などに応用されています。
まとめ
今回は、アルミニウムが磁石にくっつかない謎について解説しました。その特性を活かして、アルミニウムは様々な分野・用途で広く利用されています。特に非磁性という特徴は、医療機器からICカードリーダー、電子機器の製造まで、現代の精密技術に不可欠な要素となっています。
銅加工をはじめとした金属加工を手がける「株式会社ハタメタルワークス」では、アルミニウム製品の加工にも対応しております。お気軽にご相談ください。
監修者情報
代表取締役 畑 敬三
 株式会社ハタメタルワークスは、産業用電池や車輌機器向けの「銅加工」を専門とし、昭和10年の創業以来「誠実な対応」と「確かな製品」で信頼を築いてきました。迅速な対応により最短翌日納品が可能で、小ロットにも対応します。「小さな一流企業」を目指し、「銅加工ならハタメタルワークス」と評価されるまで成長。今後も独自の価値を提供し続けます。
詳しくはこちら
株式会社ハタメタルワークスは、産業用電池や車輌機器向けの「銅加工」を専門とし、昭和10年の創業以来「誠実な対応」と「確かな製品」で信頼を築いてきました。迅速な対応により最短翌日納品が可能で、小ロットにも対応します。「小さな一流企業」を目指し、「銅加工ならハタメタルワークス」と評価されるまで成長。今後も独自の価値を提供し続けます。
詳しくはこちら